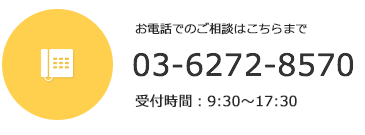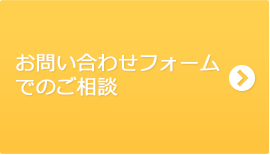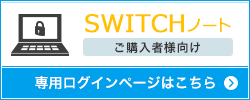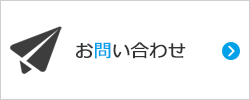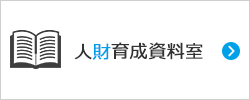HOME » 人財育成資料室 » クレーム解決塾 » Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント②
Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント②
1.カスハラ対策の現状と課題
カスハラ対策の現状として指摘しておきたいことが3つあります。
1)カスハラ対策・対応に関する会社の方針の明確化
会社としての基本方針を具体的に示すことが大変重要です。これがない状態で、例えばカスハラ対策マニュアルを作成しても、「会社としての意思」が確認できていないと社員は適切な対応をとることができません。あるいは、マニュアルがあっても、カスハラの被害を上司に報告・相談することが難しくなってしまいます。
2)相談体制の確立
社員がカスハラに遭遇した場合、すぐに相談できる体制を構築する必要があります。初動対応の適切さということからすれば、上司を中心にした管理職が初期の相談者であることが望ましいでしょう。
インターワイヤード株式会社の「カスタマーハラスメント」に関するアンケート調査によれば、カスハラの初期対応における相談者対応は以下の通りになっています。
①「上司に相談し、一緒に対応してもらった」(31.4%)
②「先輩や同僚に相談し、一緒に対応してもらった」(27.2%)
③「カスハラに気づいた上司が一緒に対応した」(19.0%)
④「カスハラに気づいた先輩や同僚が一緒に対応した」(14.5%)
しかしながら、一人での対応も31.1%という高い比率になっています
⑤「自分一人で対応した」(31.1%)
一人で対応した理由としては、
「自分一人で対応できたため、誰にも相談しなかった」(39.8%)
「そもそも一人勤務だったため」(22.0%)
が上位を占めていますが、一人で対応せざるを得なかった理由としてまずいのは、
「上司に相談したが、対応してもらえなかった」(16.9%)
「上司はカスハラに気づいたが、見て見ぬ振りをされた」(11.9%)
「先輩や同僚はカスハラに気づいたが、見て見ぬ振りをされた」(9.3%)
という比率がかなり高いということです。
こうした状態が続けば社員のメンタル面に影響が出てくることは十分予測されることです。
3)社員のメンタルヘルスへの対応
上記のことからも、社員に対するメンタルヘルス対策もしっかりと講じる必要があります。もし、社員の不調を感じることがあれば、早い段階での対応が必要になります、保険スタッフによる面談や医療機関への受診を勧めるなど、適切な支援を講じる必要があります。
そして、大切なことはこうした状況を防止するためにも『カスハラへの対応は必ず複数で行う』ことを原則にして、その対策をとることです。
関連するカテゴリーの記事
- Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント④
- Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント③
- Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント②
- Ⅷ 不当要求とカスタマーハラスメント①
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅶ クレーム解決の成功のポイント・失敗のポイント
- Ⅵ 電話クレーム対応の基本
- Ⅵ 電話クレーム対応の基本
- Ⅴクレーム初期対応の注意点
- Ⅴクレーム初期対応の注意点
- Ⅴクレーム初期対応の注意点
- Ⅳクレームにおける謝罪の意義と心構え
- Ⅲグッドマンの法則とクレームの関係性
- Ⅱクレームの発生原因を考える
- Ⅱクレームの発生原因を考える
- Ⅰクレームと企業の対応姿勢~原則3
- Ⅰクレームと企業の対応姿勢~原則2
- Ⅰクレームと企業の対応姿勢~原則1